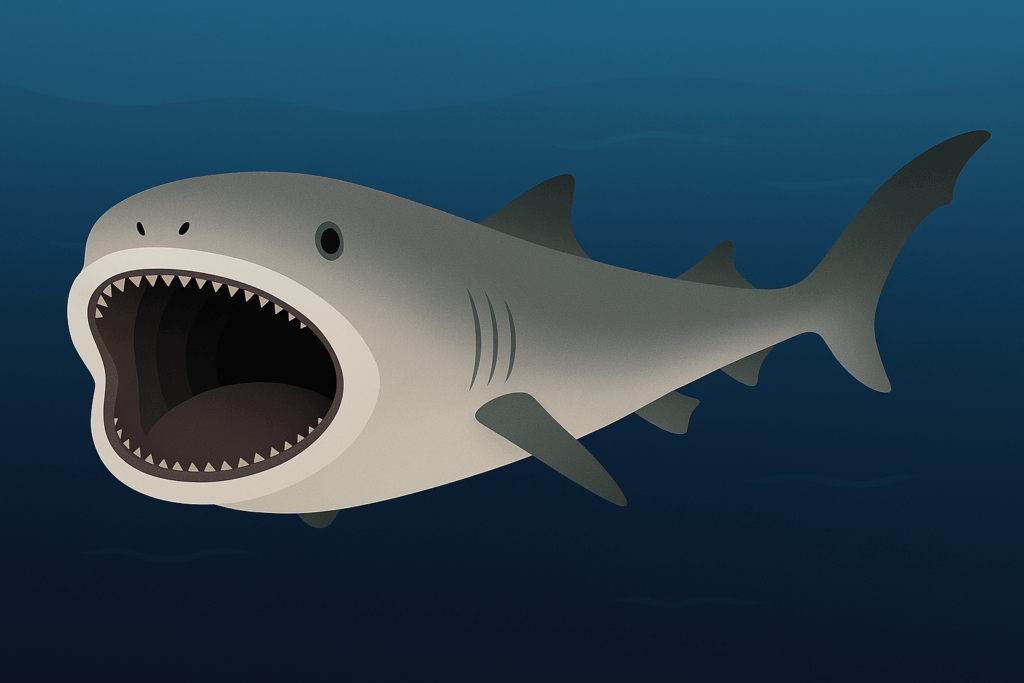メガマウスザメ(Megamouth Shark)図鑑
1976年に発見された「幻のサメ」。巨大な口を開けてプランクトンを食べる、深海の穏やかな巨人です。
基本情報
| 和名 | メガマウスザメ |
|---|---|
| 英名 | Megamouth Shark |
| 学名 | Megachasma pelagios |
| 分類 | ネズミザメ目 メガマウスザメ科 メガマウスザメ属 |
| 体長 | 平均 4〜6m(最大記録:約7.5m) |
| 体重 | 大型個体で 1t を超えると推定 |
| 生息域 | 外洋の中層〜深場(200〜1,000m)。昼は深く、夜は浅い層へ上がる日周鉛直移動を行う。 |
| 分布 | 世界の熱帯〜温帯域に散発的。日本近海(相模湾・駿河湾など)でも記録あり。 |
| IUCNレッドリスト | 低懸念(LC) |
| 危険度 | ★☆☆☆☆(1:人に対して実質無害/温和・濾過食) |
形態
名前の通り、体長に比して非常に大きな口を持つのが最大の特徴です。
- 口:内側は銀色に輝き、光を反射する構造になっています。これはプランクトンをおびき寄せるためと考えられています。
- 体型:ずんぐりとして柔らかく、遊泳力はあまり高くありません。
- 濾過器官:鰓(えら)には「鰓耙(さいは)」というフィルターが発達しており、海水ごと吸い込んだプランクトンをこし取ります。
生態
食性:三大プランクトン食サメ
ジンベエザメ、ウバザメと並ぶ、世界に3種しかいない「プランクトン食」のサメです。主にオキアミやカイアシ類、クラゲなどを濾過摂食します。
行動:日周鉛直移動
昼間は水深200〜1000mの深海に潜み、夜になるとプランクトンを追って水深10〜20mの表層近くまで浮上します。この行動は「日周鉛直移動」と呼ばれます。
繁殖
詳細は未解明ですが、ネズミザメ目の特徴から「胎生(卵食性)」である可能性が高いと考えられています。
人との関わり・危険性
非常に温和で、プランクトンしか食べないため、人に対する危険性はありません。
深海に生息するため遭遇することは極めて稀ですが、定置網などに混獲されることがあります。世界での発見例はまだ少なく、その多くが日本近海での記録であることから、日本はメガマウス研究の重要拠点となっています。
トリビア
- 発見の歴史:1976年にハワイ沖で米海軍の船のアンカーに偶然引っかかって発見されました。それまで存在すら知られていなかった「20世紀最大の発見」の一つです。
- 光る口:口の中が発光する(または光を反射する)ことで、餌となるプランクトンをおびき寄せているという説があります。
まとめ
メガマウスザメは、巨大な口と濾過摂食という特殊な生態をもつ、幻の深海ザメです。発見から日が浅く、生態にはまだ多くの謎が残されています。日本の海は、この珍しいサメが比較的多く見つかる、世界でも稀有な場所です。
関連
メガマウスのぬりえ
FAQ(よくある質問)
どこで見られますか?
熱帯〜温帯の外洋で散発的に記録されます。日本では相模湾・駿河湾、千葉県沖などで比較的多く見つかっています。
人を襲いますか?
いいえ。温和な濾過食で人に対する攻撃性は知られていません。
どれくらい大きくなりますか?
平均で5m前後、最大で7mを超えると推定されています。
飼育は可能ですか?
深海の環境と広大なスペースが必要なため、長期飼育の実績は事実上ありません。水族館では標本や剥製が見られます(鴨川シーワールドなど)。
保護状況は?
IUCN は LC(低懸念)としていますが、データ不足が指摘され、継続的な調査が必要です。