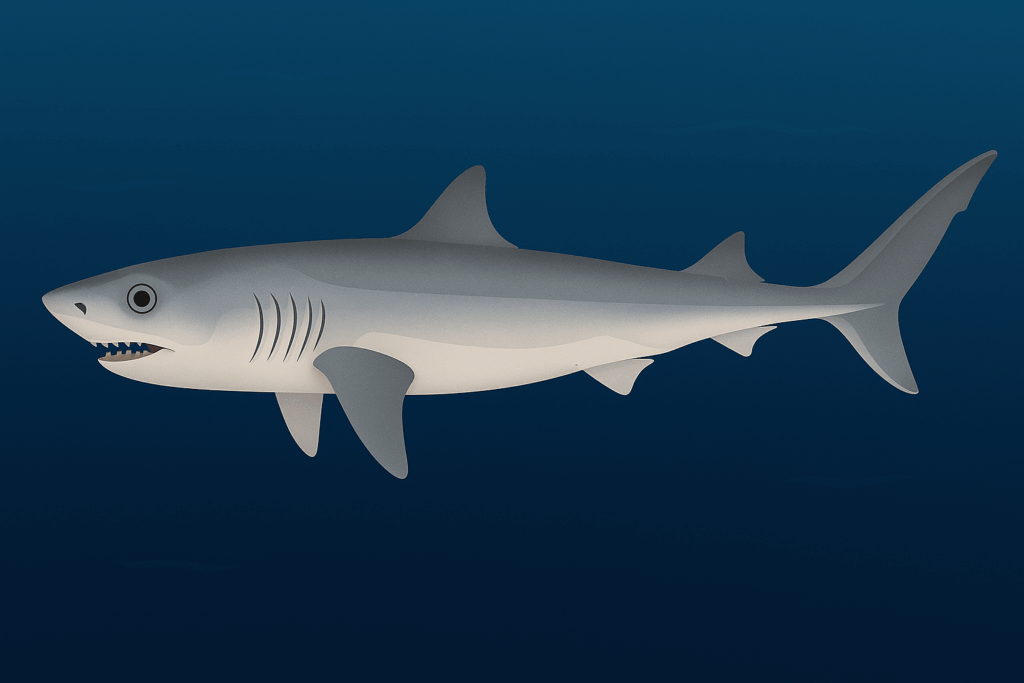ニシネズミザメ(Porbeagle)図鑑
ホホジロザメの近縁種。ずんぐりした体型で冷たい海を好む「危急種(VU)」。人への危険性や、ホホジロザメとの違い、生態を解説します。
基本情報
| 和名 | ニシネズミザメ |
|---|---|
| 英名 | Porbeagle |
| 学名 | Lamna nasus |
| 分類 | ネズミザメ目 ネズミザメ科 ネズミザメ属 |
| 体長 | 2〜3.5m |
| 体重 | 90〜230kg |
| 生息域 | 寒帯〜温帯の外洋、水深20〜700m |
| 分布 | 北大西洋(北米〜欧州沿岸)、南半球の温帯域(南アメリカ、南アフリカ、ニュージーランド周辺など) |
| IUCNレッドリスト | 危急(VU) |
| 危険度 | ★★☆☆☆(2:大型だが人への攻撃性は低い) |
形態
ニシネズミザメはネズミザメ科に属する中〜大型のサメで、ずんぐりとした頑丈な体つきが特徴です。
- 尾鰭は半月形(ルナ型)で、高速遊泳に適応しています。
- 体色は背が灰青色〜青黒色、腹は白。胸鰭の裏に暗色斑があるのが識別ポイントです。
- 体はホホジロザメに似ていますが、より小型で、吻が鋭く尖っています。
生態
行動
外洋性の回遊魚で、季節や水温に応じて広範囲を移動します。寒帯〜温帯域の冷たい海を好み、北大西洋や南半球の温帯海域に分布。
食性
硬骨魚(ニシン、サバ、タラなど)を主に捕食します。イカや甲殻類を食べることもあり、遊泳力を生かして活発に獲物を追います。
繁殖
卵食仔胎生。母体内で孵化した仔ザメは未受精卵を食べて成長します。出産数は2〜4匹と少なく、繁殖力は低いです。
寿命
30〜40年ほどと長寿で、性成熟に8〜13年と時間がかかるため、資源回復が難しい種です。
人との関わり・危険性
ニシネズミザメは人に対して攻撃的ではなく、ダイバーとの遭遇例でも事故はほとんどありません。危険度は低いものの、体が大きいため不用意な接近は避けるべきです。
一方で漁業資源としての利用が古くからあり、肉や肝油、ヒレが利用されてきました。そのため乱獲が進み、現在は資源量が大幅に減少しています。IUCNでは「危急(VU)」に分類され、国際的な漁獲規制や保護の対象になっています。
トリビア
- 名前の由来:「Porbeagle」は「豚(porpoise)」と「ビーク(嘴)」が組み合わさった言葉で、体型や吻の形から名付けられたといわれます。
- ホホジロザメの親戚:同じネズミザメ科に属し、外見や生態に共通点が多い近縁種です。
- 漁業との関わり:かつては北大西洋で重要な漁獲対象でしたが、現在は資源減少により厳しい管理が行われています。
- 回遊距離:標識調査で数千km単位の移動が確認されており、外洋を広く回遊していることが分かっています。
まとめ
ニシネズミザメは、寒帯〜温帯の外洋を回遊する中〜大型のサメで、強力な尾鰭を持ち活発に硬骨魚を追う捕食者です。人に危険はほとんどありませんが、成長が遅く繁殖力も低いため、漁業圧によって個体数が減少しています。保護管理が重要なサメのひとつです。
FAQ(よくある質問)
Q1. ニシネズミザメは人を襲いますか?
基本的に人を襲うことはなく、危険性は低いサメです。
Q2. どのくらい大きくなりますか?
平均で2〜3m、最大で3.5mに達します。体重は200kgを超えることもあります。
Q3. 何を食べていますか?
ニシン、サバ、タラなどの硬骨魚を主に捕食します。イカや甲殻類を食べることもあります。
Q4. どこで見られますか?
北大西洋(アメリカ東岸〜ヨーロッパ)、南アフリカ、南アメリカ、ニュージーランドなど温帯域の外洋で見られます。
Q5. なぜ絶滅の心配があるのですか?
成長が遅く出産数も少ないため乱獲の影響を強く受けます。過去の過剰漁獲で資源が減少し、現在も回復が遅れているため IUCN では「危急(VU)」に指定されています。