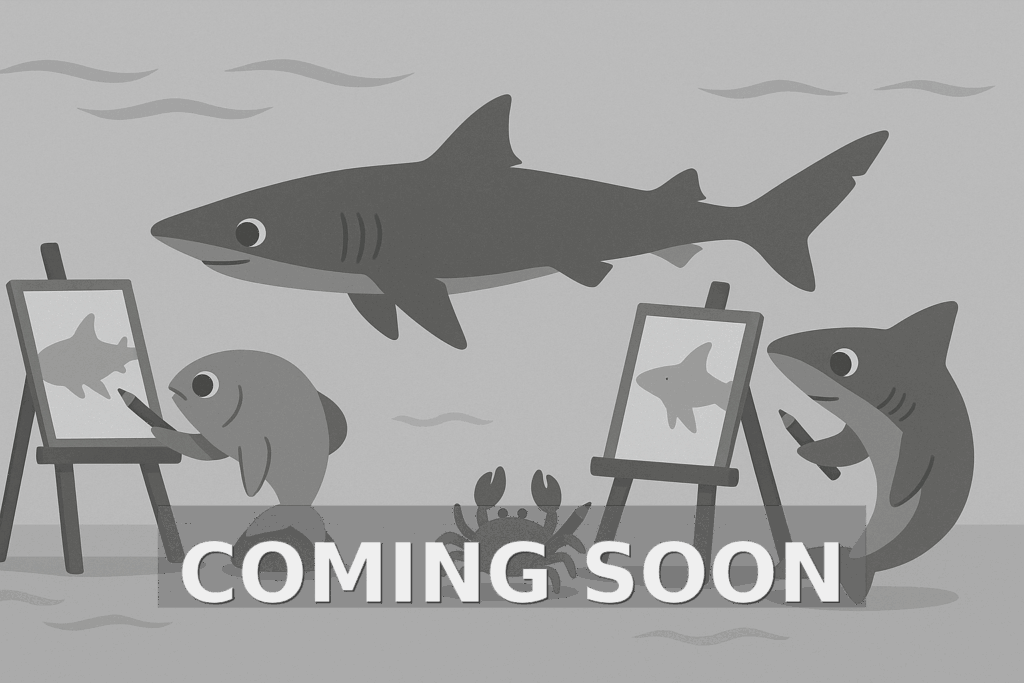基本情報
和名:メガマウス
英名:Megamouth Shark
学名:Megachasma pelagios
体長:4〜7m(最大7.5m近い記録もある)
体重:0.5〜1.5トン
生息域:外洋・中層(水深200〜1000mを行き来する)
分布:世界各地でまれに発見される(太平洋・インド洋・大西洋で記録あり、日本でも複数例)
IUCNレッドリスト:低懸念(LC)
危険度:★☆☆☆☆(1:人に危険性はほぼない)
形態
メガマウスは、1976年にハワイ沖で初めて確認された、比較的新しく発見された大型サメです。
名前の通り、体長に比して非常に大きな口を持ち、口の幅は1mを超えることもあります。
体は柔らかくゼラチン質に富み、筋肉質の外洋サメに比べて「だらん」とした印象。
背は黒〜灰褐色、腹は白色。
口の内側は反射的な白や銀色の模様があり、光を反射してプランクトンを誘引する役割を持つと考えられています。
生態
食性:ジンベエザメやウバザメと同様、プランクトン食。海水を大量に取り込み、鰓耙で濾して動物プランクトンや小型魚類を捕食します。
行動:日周鉛直移動(diel vertical migration) を行い、昼間は深場(水深500〜1000m)に潜み、夜間になると表層(水深200m付近)へ上昇します。これは餌となるプランクトンが夜間に浮上するのに合わせた行動です。
回遊:世界各地で発見されますが、その出現は非常にまれ。記録数はまだ200例程度しかなく、全体像は謎に包まれています。
繁殖:胎生と考えられていますが、詳細は不明。
人との関わり・危険性
メガマウスは人に危険性のないサメで、温和な性質を持ちます。ダイバーによる遭遇例もありますが、攻撃性は皆無とされています。
その珍しさから、発見されると学術的にもニュースとして取り上げられることが多く、標本や映像は貴重な研究資料となります。日本でも駿河湾や相模湾などで複数回発見され、世界的に見ても重要な観察例が残されています。
トリビア
発見の新しさ:最初の記録は1976年、アメリカ海軍の艦に絡まった個体。このため「新参の巨大ザメ」として世界を驚かせました。
個体数の謎:世界各地で記録が散発的にあるだけで、推定個体数も不明。深海生活が多いため調査が難しいサメです。
光る口の役割:口内の反射模様は発光プランクトンを模倣して獲物を誘う「ルアー」として機能するのではないかと考えられています。
巨大プランクトン食サメの仲間:ジンベエザメ、ウバザメと並ぶ「三大プランクトン食サメ」の一角です。
まとめ
メガマウスは、1976年に発見された比較的新しい種類の巨大サメで、謎の多い外洋性プランクトン食サメです。夜間に表層に現れる習性や巨大な口、柔らかい体といったユニークな特徴から、研究対象としても人気があります。まだ発見例が少なく、今後の調査でその生態が解き明かされることが期待されています。
FAQ(よくある質問)
Q1. メガマウスは人を襲いますか?
A. いいえ。人に危険性はなく、性格も温和なサメです。
Q2. どのくらいの大きさですか?
A. 体長4〜7m、体重は0.5〜1.5トンほどになります。
Q3. どこで見つかりますか?
A. 太平洋・インド洋・大西洋で散発的に発見されます。日本近海(駿河湾や相模湾など)でも複数例報告があります。
Q4. いつ発見されたのですか?
A. 初めての発見は1976年、ハワイ沖でアメリカ海軍の艦に偶然引っかかった個体でした。
Q5. 絶滅の心配はありますか?
A. IUCNでは「低懸念(LC)」に分類されています。ただし記録例が少なく、生態の多くが不明であるため、今後のモニタリングが重要とされています。
参考文献・出典
- IUCN Red List of Threatened Species https://www.iucnredlist.org/
- FishBase https://www.fishbase.se/
- FAO Fisheries & Aquaculture http://www.fao.org/fishery/