ネコザメ(Japanese Bullhead Shark)
岩礁帯や海藻域を好む、夜行性の底生サメ。らせん状の卵のう(卵しょう)で知られる。
- 和名
- ネコザメ
- 英名
- Japanese Bullhead Shark
- 学名
- Heterodontus japonicus
- 分類
- ネコザメ目 ネコザメ科 ネコザメ属
- 体長
- 平均 0.8〜1.2m(最大 約1.5m 前後)
- 体重
- 個体差あり(十数kg 級の報告)
- 生息域
- 温帯おんたい域の沿岸〜浅海・岩礁帯・海藻域。主に底層で活動。
- 分布
- 北西太平洋(日本列島〜朝鮮半島・中国東岸)。地方分布に偏り。
- 好適水温の目安
- およそ 10〜22℃(地域差あり)
- IUCNレッドリスト
- 低懸念ていけねん(LC)
- 危険度
- ★☆☆☆☆(1:人に対して実質無害/臆病・おとなしい)
- 近い特徴のサメ
-
シマネコザメ(Heterodontus zebra):同属・らせん卵。
カリフォルニアネコザメ(H. francisci):同属・夜行性・殻類食。
ポートジャクソンネコザメ(H. portusjacksoni):同属・らせん卵が有名・背びれ前のとげ。
形態
丸みのある頭部とうぶと短い吻ふん、発達した眉間部が特徴。背びれは二基にきで各かく前方ぜんぽうにとげ(棘きょく)を持つ。体色たいしょくは黄褐色〜灰色はいいろで、不規則な暗色あんしょくの帯状・斑点が入る。口の歯列しれつは 前方ぜんぽうが小尖しょうせん歯、奥歯は臼状(クラッシャー)で、貝・甲殻類をすりつぶすのに適している。胸びれ・腹びれは広く底生ていせい生活に向いた形。
生態・食性
夜行性やこうせいが強く、昼間は岩陰や海藻帯で休むことが多い。夕方〜夜間にかけて活動が上がり、貝類(巻き貝・二枚貝)・甲殻類(カニ・エビ)・ウニ類など殻をもつ底生ていせい生物を主食しゅしょくとする。嗅覚・触覚的な探索たんさくと、臼歯での破砕はさいに優れる。遊泳は短距離で、テリトリー内をのし歩くように動く。
行動
ナイトレンジ(夜間行動圏)をもつ個体が多く、定住性が比較的強い。単独またはゆるい小集団。季節きせつにより浅場とやや深場を行き来する。俊敏では外洋型に劣るが、狭い岩場での索餌能力は高い。
繁殖
卵生。雌はらせん状じょうの卵しょう(卵のう)を二個ずつ産み、岩のすき間にねじ込むように固定していく。
産卵期は地域差があるが春〜夏に多く、抱卵ほうらん数すう(シーズンの総計)は十数個〜数十個。
卵しょう内での発生はゆっくりで、ふ化まで 7〜12か月程度ことが多い。ふ化直後の仔魚は 15〜20cm
前後。性成熟は遅めで、寿命は数十年クラスと考えられている。
人との関わり・危険性
おとなしく、人に対する攻撃性は低い。背びれ前の棘きょくで不意にけがをする事例じれいがあるため、観察・採捕時は手袋・慎重な取り扱いが望ましい。沿岸の定置網・刺し網などで混獲されることがあるが、統計的な事故は稀。サメの危険度としては低位で、適切な距離の保持・むやみに触れないといった基本ルールで十分に安全を確保できる。
トリビア
- 学名 Heterodontus は「異いなる歯」の意い。前歯(つかみ取り用)と奥歯(すりつぶし用)がはっきり分化。
- らせん卵しょうは、波や流れでも岩の割れ目に固定されやすい“ねじ構造”。
- 夜行性のため、昼は動きが少ない。水族館では岩陰いわかげで休む姿が見られる。
まとめ
ネコザメは、殻こうを砕くだく臼歯とらせん卵しょうに象徴される「底生×夜行性」タイプ。沿岸の岩礁・海藻帯にくらし、人とのトラブルは少ない。地域資源としての管理や、生息地の保全(藻場・岩礁帯の良質化りょうしつか)が、種しゅの将来にもつながる。
関連
- シマネコザメ(Zebra Bullhead Shark)(らせん卵しょう)
- カリフォルニアネコザメ(同属・臼歯きゅうし発達)
- ポートジャクソンネコザメ(らせん卵しょう・背びれ棘)
- サメの生態(ハブ)
- サメの雑学(ハブ)
- サメの危険(ハブ)
ネコザメに触れる!水族館ガイド
ネコザメは非常におとなしい性格のため、全国の水族館の「タッチプール(ふれあいコーナー)」の定番メンバーです。
見るだけでなく、実際にあの「ザラザラしたサメ肌」を体験できる貴重なサメです。
実際に触れる主な水族館
- アクアワールド茨城県大洗水族館(茨城県):サメ飼育数日本一の水族館。タッチプールで常時ネコザメに触れることができます。
- 横浜・八景島シーパラダイス(神奈川県):「ふれあいラグーン」にて、ネコザメやドチザメとのふれあい体験が人気です。
- 下田海中水族館(静岡県):海に浮かぶ水族館。「ふれあいの海」でネコザメに触ることができます。
- 大阪海遊館(大阪府):「モルディブ諸島」ゾーンの体感エリアで、サメやエイに触れることができます。
ネコザメの背びれには鋭いトゲがあります。触るときは必ず係員さんの指示に従い、頭や背びれではなく「背中や体」を優しく触るようにしましょう。
ネコザメの塗り絵
FAQ(よくある質問)
どこに生息していますか?
日本列島を中心とする北西太平洋の沿岸えんがん〜浅海部。岩礁帯・海藻域を好みます。
何を食べますか?
巻き貝・二枚貝・カニ・エビ・ウニなど。臼歯でかたい殻を砕くのが得意です。
人に危険ですか?
基本的に臆病・おとなしく、人への攻撃は稀まれです。背びれ前の棘きょくでの不意の負傷に注意。
卵はどうやって産みますか?
らせん状じょうの卵しょうを二個にこずつ産み、岩のすき間にねじ込んで固定します。ふ化まで長期間かかります。
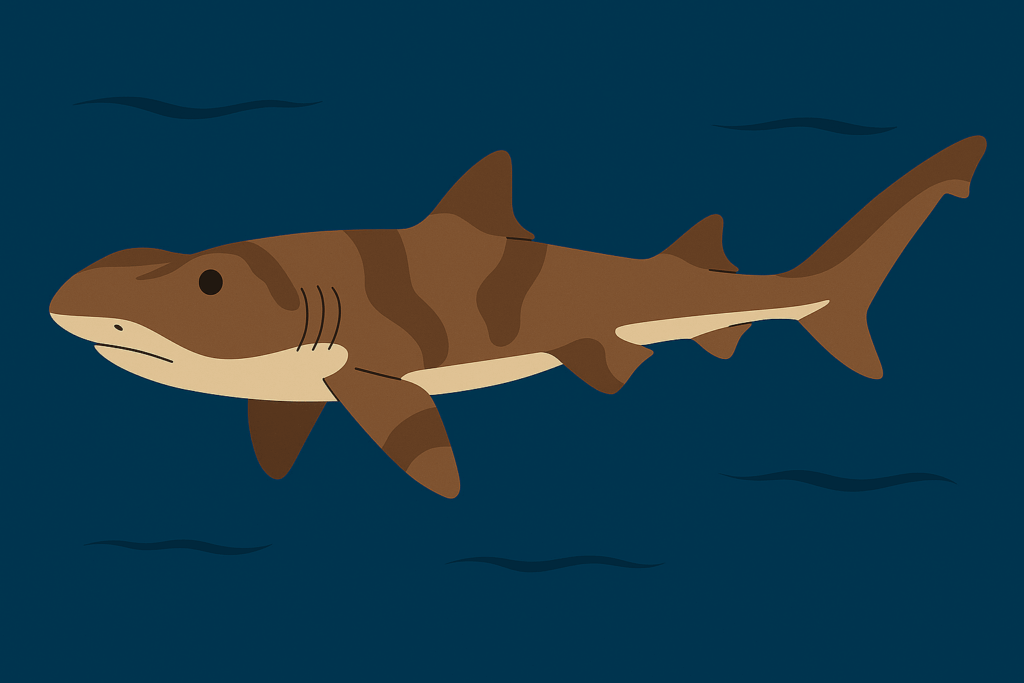
🦈 管理人の「サメ愛」メモ:息子との観察日記
初めてネコザメを見た時の第一印象は、親子そろって「なんでこれがネコ?」でした(笑)。
調べてみると、目の形や、耳のように張り出した頭の形が猫に似ているからだとか。言われてみれば、海底でじっとしている姿は、香箱座りした猫に見えなくもありません。
息子の感想は「サメなのに顔が怖くない!かわいい!」。
実際にアクアワールド茨城県大洗水族館のタッチプールで触れる機会があったのですが、ザラザラしたサメ肌の感触に「うわ〜本物だ!」と大感動していました。
そして最近、息子がとんでもないことを言い出しました。「ネコザメ飼いたい!」
実はネコザメ、底生でおとなしいため、超富裕層でなくても「個人宅でギリギリ飼育可能な唯一のサメ」とも言われているんです(それでも巨大な水槽と設備が必要で大変ですが…)。
いつか我が家に「海の猫」を迎える日が来るのでしょうか…。